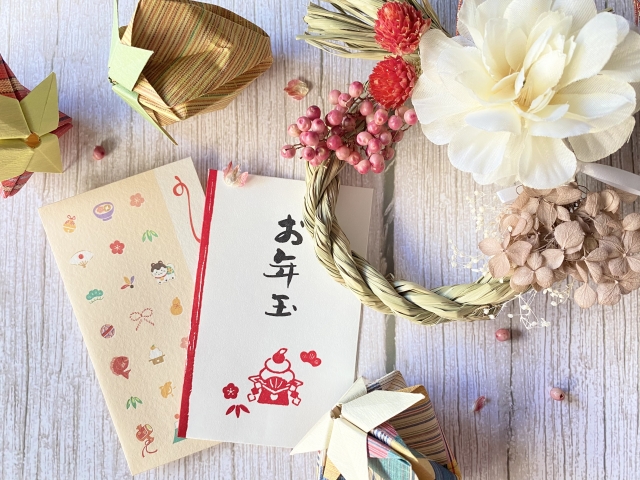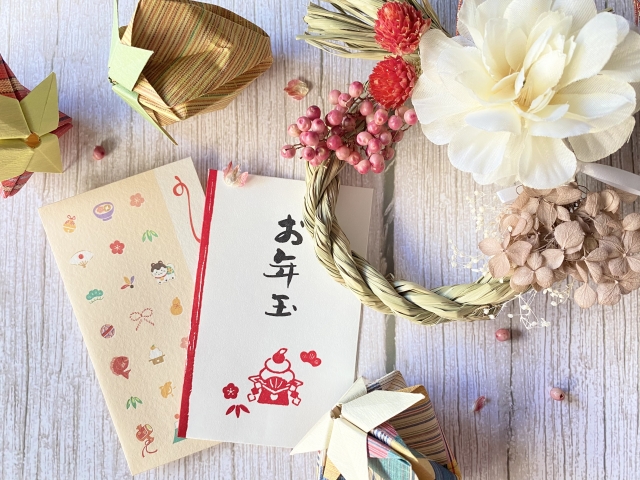
写真はイメージです
正月は家族や親戚が顔を合わせ、食卓を囲んだり子どもがお年玉を受け取ったりと、子どもにとって楽しみの多い年中行事です。
その一方で、お年玉を渡す立場の大人にとっては、適切な金額や渡すタイミングなど、悩むポイントが少なくありません。
この記事では、お年玉の意味や由来に触れながら、中学生に渡す際の相場や、相手に失礼にならない渡し方の作法について、分かりやすく解説いたします。
お年玉の意味と由来について
ここでは、お年玉の意味と由来について紹介いたします。
お年玉の意味は?
お年玉とは、新しい年の始まりに子どもへ手渡す祝いの贈り物であり、健やかな一年や豊かな成長を願う思いを形にしたものです。
単なる金銭ではなく、「今年も元気に過ごせますように」「努力が実を結ぶ一年になりますように」といった励ましや期待を込めて渡されます。
近年では子どもの楽しみやお小遣い的な意味合いも強くなりましたが、もともとは年頭に目上から目下へ福を授けるという考え方が受け継がれています。
さらに、親族間の交流を深めるきっかけとなり、子どもがお金の扱い方や価値を学ぶ機会にもつながる点も、お年玉の重要な役割といえるでしょう。
お年玉の由来は?
お年玉の起源は、日本の古くから伝わる正月の習わしに由来します。新年には歳神(としがみ)と呼ばれる神が各家へ訪れ、その年の恵みや生命力、五穀豊穣を授けると考えられていました。
人々は歳神に供えた鏡餅を家族で分け合い、その餅を「御年魂(おとしだま)」として子どもに与え、一年の健やかな成長や無病息災を願いました。
やがて、この餅を分配する風習が変化し、餅の代わりに貨幣を包んで渡す形へと移り変わっていきます。この過程で贈る対象が子ども中心となり、現在のようにお金を渡すお年玉の習慣が定着したとされています。
中学生のお年玉の相場について
中学生のお年玉の相場について解説いたします。
とある中学生のお年玉の相場の調査にて以下のような結果になりました。
1位:3,001~5,000円(49.1%)
2位:5,001~10,000円(29%)
中学生になるとおもちゃだけでなく、趣味・部活動・衣類・交際費など、お年玉の使い道が広がる傾向があります。
そのため、小学生の頃より金額が上がり、5,000円前後を目安とする家庭が一般的です。
お年玉袋へのお金の入れ方とマナーについて
ここからは、お年玉袋へのお金の入れ方とマナーについて解説します。
お年玉袋の選び方について
お年玉を包む際に使うポチ袋は、子どもに人気のキャラクターデザインや、遊び心のある柄が選ばれることが多いです。
メッセージ入りの袋やユニークな図案を選べば、受け取った子どもが喜ぶだけでなく、渡す場で会話が弾むきっかけにもなります。
一方で、渡す相手の家庭との関係性によっては、水引の付いた格式あるタイプの袋を使用したほうが好印象となる場合もあります。
自分の子どもや孫、甥・姪に渡す場合は形式にこだわる必要はありませんが、仕事関係の方のお子さまなど礼儀を求められる場面では、配慮を欠かさないことが大切です。
お年玉袋の書き方について
お年玉袋の記入方法は、一般的に表面左上へ受け取る子どもの名前を、裏面左下へ渡し手の名前を添える形が基本となります。
こうした配置にすることで、誰に渡すものか、誰から贈られたのかが一目でわかりやすく、受け取る側にも丁寧な印象を与えます。
文字は読みやすく、はっきり書くことを心がけると良いでしょう。
お札の折り方と入れ方について
紙幣でお年玉を包む際は、人物の肖像が見える面を外側にし、左側から内側へ向かう形で三つ折りにして袋へ入れるのが基本です。
袋の大きさによっては別の折り方が必要になることもありますが、四つ折りは縁起が悪いとされるため避けるのが望ましいとされています。
硬貨を渡す場合は、模様や図柄が正面にくるように袋の向きに合わせて収めます。さらに、お札を準備する際は可能な限り新札を用いることで、受け取る側に丁寧で気持ちのこもった印象を与えることができます。
金額や縁起に気をつける
お年玉は新年を祝う贈り物であるため、縁起の悪さや苦痛を連想させる金額は避けるのが一般的な心配りです。
なかでも「死」を想起させる4や、「苦」に通じる9を含む数字は、不祝儀を思わせることがあるため控えるのが望ましいとされています。
さらに、贈り先が喪中の場合は、年賀の挨拶やお年玉を渡さないのが基本的なマナーです。それでも子どもへ気持ちを伝えたいときは、派手なものを避けた落ち着いたデザインの袋を選び、「お小遣い」といった名目で渡すと、穏やかに配慮を示すことができます。
お年玉をあげる年齢や金額について相談する
お年玉を準備する際は、一般的な目安だけでなく、家族や親戚の間で決まっている取り決めを事前に確認し、共有しておくことが大切です。金額にばらつきがあると、子ども同士が比べて不公平に感じたり、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
また、他の子に渡した金額と自分の子どもが受け取った額に大きな差が生じないよう、全体のバランスにも配慮しましょう。各家庭の考え方や親族間の慣習が曖昧な場合は、事前に話し合って基準を定めておくと、安心して準備を進めることができます。
まとめ

お年玉の額は、子どもの年齢や成長に合わせて段階的に増やしていくのが一般的です。単に相場を基準とするだけでなく、親族や身近な大人がどの程度の金額を渡しているかも把握し、周囲とのバランスを考えた渡し方を心がけるとよいでしょう。
また、お年玉は子どもにとってお金の扱いを学ぶ良い機会でもあります。年齢ごとの目安や渡す際のマナーを参考にしながら、相手への思いやりを込めて用意することで、より温かい贈り物になります。